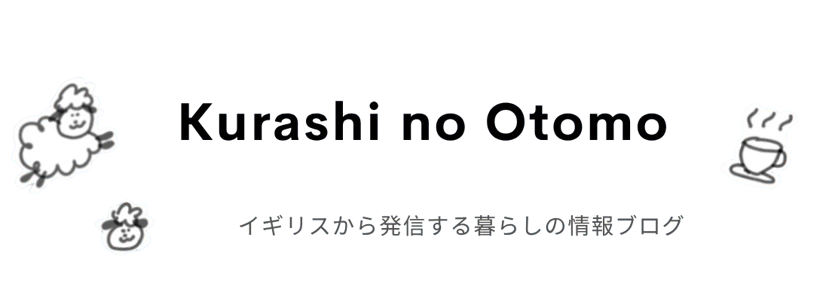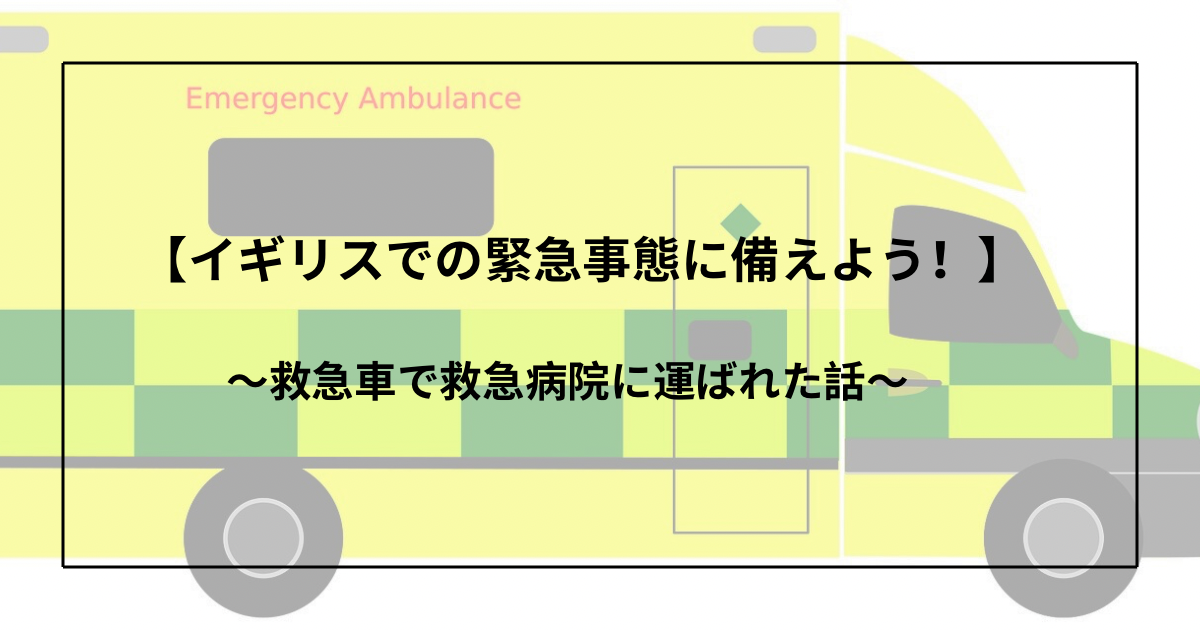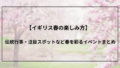イギリスで救急車を呼ぶには?緊急事態時の対応・実際に救急車で搬送された体験についてまとめ
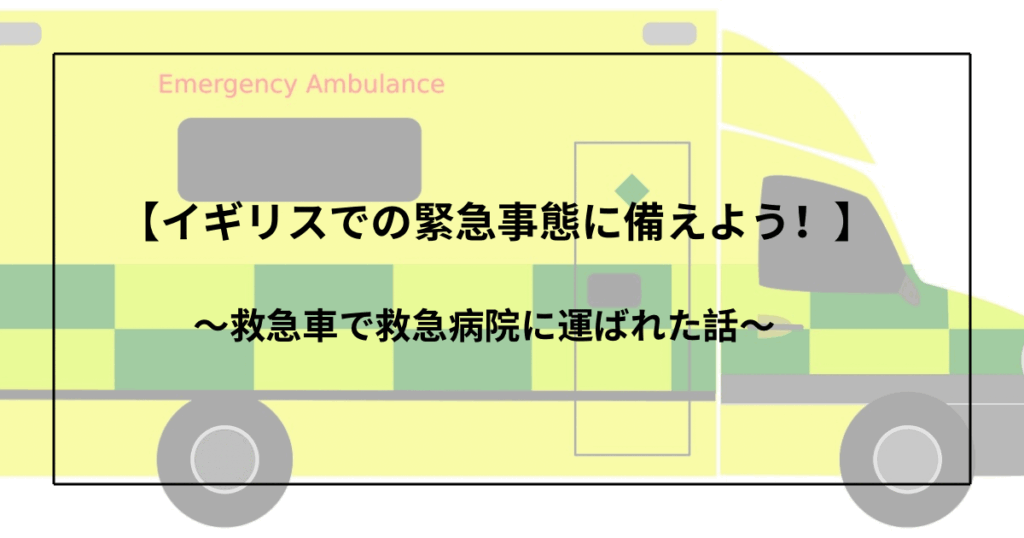
いつかの時のために備えておきたい、緊急事態時の対応。
日本にいてもそうですが、イギリスに住んでいれば尚更しっかりと備えておきたいもの。
先日救急車に乗ってA&E(救急病院)に搬送される体験をしました。
日本にいた時すら乗ったことのない救急車にまさかイギリスで乗る日がくるとは夢にも思いませんでしたが、改めて自分や家族のために緊急事態時の対応をしっかり頭に入れておかなくては…!と思い知らされました。
この記事では私の経験と共に、イギリスの医療のための緊急事態時の対応についてまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
イギリスの医療制度

まずは簡単にイギリスの医療制度について確認しておきます。
イギリスの医療制度は以下の二つに分かれます。
- 国民保険 National Health Service ( 一般的にNHSと呼ばれています )
- プライベート医療
国民保険( NHS )
NHSと呼ばれる国民保険は、長期滞在の方なら必ず加入していると思います。
受診は原則無料で、救急医療も重篤患者以外はNHSでのみ提供されています。
プライベート医療
全て自己負担での受診。原則、救急対応は提供されていません。
医療が必要な時の連絡先・場所
- 111に電話
24時間いつでも医療のアドバイスが受けられるフリーダイヤル。(オンライン・NHSのアプリ上でも利用可)
GPが開いていないとき、救急車を呼ぶべきかどこに問い合わせたらいいか分からないときに利用します。適切な処置をガイドしてくれて、GPと連携して症状を記録してくれます。 - 999に電話
救急の対応が必要な時にかけるフリーダイヤル。救急隊をその場に派遣してくれて、緊急の場合などはそのまま救急車で搬送されます。 - A&E( Accident and Emergency ) へ行く
救急車に乗らなくても自力で行ける場合は、A&E(救急病院)の外来へウォークインで入ることもできます。
受付で登録をして、そのまま症状に応じて待つ必要があります。 - UTC( Urgent Treatment Centre )へ行く
A&Eに行くほどの症状ではないが、処置が必要なとき。予約は必要なく、A&E同様ウォークインで入ることができます。
111へ電話すると、UTCへ行くよう指示があることも。その際は111からUTCへ症状や詳細が事前にシェアされているので受付で伝える必要があります。UTCはA&Eと同じ建物内に併設されていることも。
実際に救急車でA&Eへ搬送された体験について
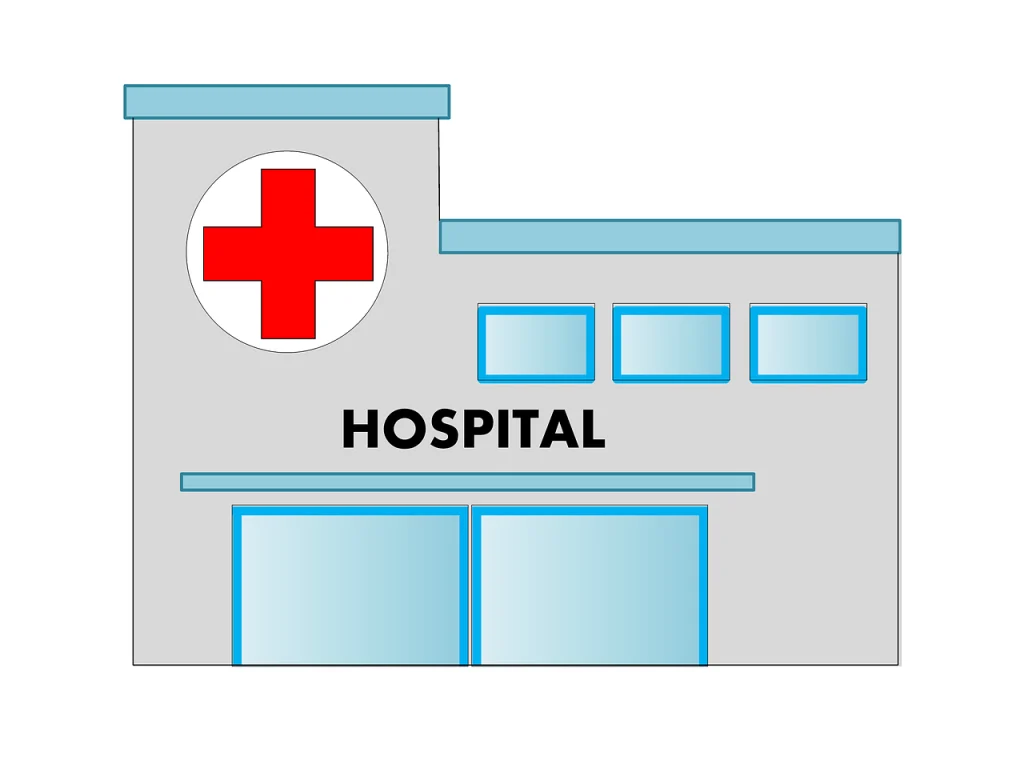
先日、人生で初めて救急車に乗る体験をしました。
きっかけは軽い火傷のために飲んでいた抗生物質(GPから処方されたもの)で、そこに含まれるペニシリンにアレルギー反応を起こしたことでした。全身に蕁麻疹の症状が出て、喉が腫れて呼吸も少し浅くなるような状態でした。
最終的に救急車でA&Eへ行くまでの流れとその時の対応は以下の通りです。
| 水曜日 午後 | 蕁麻疹の症状が出始め、抗生物質の使用をストップする。 |
| 水曜日 22時 | 蕁麻疹が全身に広がり始め、111に電話する。症状を説明し質問に答える。数時間後に確認の電話を入れると言われる。 |
| 3時間後 | 111からその後の症状について確認の電話がくる。アレルギー用の薬を飲むよう勧められ、GPに症状について連携しておくと伝えられる。 |
| 木曜日 朝 | GPから電話がかかってくる。111から症状はすでに伝えられており、その日の枠で予約を取ってくれる。 |
| 木曜 正午 | GPで診察してもらう。薬を処方され、症状が悪化した場合は再度111へ電話するよう指示される。 |
| 金曜 朝 | 症状が悪化したため111へ電話。祝日でGPが休みのため、他の病院を予約される。 |
| 2時間後 | 病院に行く直前で呼吸が浅くなり始め、999へ電話する。5分経たずに救急隊員が自宅まで来て、症状を診てもらう。念のため、救急車でそのまま近くのA&Eへ行く。 |
| 1時間後 | A&Eで診察してもらい、帰宅する。 |
NHSのサービスを有効に利用するために
長期滞在の方であれば必ず保険料を払って加入しているNHS。
プライベート医療とは違い、GPの予約がなかなか取れなかったり、待ち時間がとにかく長かったりとデメリットもたくさんありますが、適切な医療サービスを受けるために有効に使うよう努めることが大切です。
YMSで暮らしていた2年間は、病気などに縁がなく一度も利用することのなかった私ですが、ここに来てGPを利用する機会が増え、救急車も乗る体験をしたことから学んだことは以下の三点です。
✅ GPにすぐに連絡が取れない時は、躊躇わず111に電話(あるいはオンライン)してGPに連携してもらう。
✅ 自分の持つアレルギーや過去の病気などはしっかりと医師に伝え、GPに記録として残してもらう。
✅ 緊急の際の連絡先、行くべき場所は把握しておき、もしもの時に焦らず対応できるよう備える。
111への連絡は、医療アドバイスを受けるためだけでなく、GPへの連絡口としても有効です。
必要な場合はGPの当日枠での予約が可能になったり、症状をGPと連携して記録してくれるので、今後受ける医療サービスにも役立ちます。
GPによってはオンライン予約だけしか受け付けていない場所もあるので、急いで診てもらいたいときは111に電話することでGP予約への近道にもなります。
GPに自分の記録を残してもらうこともとても大切です。今後処方される薬や医療に関わるので、医師にしっかりと伝えるようにしましょう。
私の場合は今回の一件でペニシリンの含まれる薬は服用できないことが分かったので、情報として記録され、次回以降は処方されないようになっています。記録に残っているとはいえ、毎回医師に直接伝えることも重要です。
緊急の際の連絡先や行くべき場所は、緊急事態になってからでは遅いので、普段から確認しておくようにしておくことが大切です。
まとめ

もしもの時に備えるために、イギリスでの医療制度や緊急連絡先についてしっかりと確認しておくことが何よりも大切です。
緊急事態以外にも、NHSの医療サービスを有効に利用できるよう知識を深めておくと、今後自分が受けるサービスにも良い影響が出ると思います。
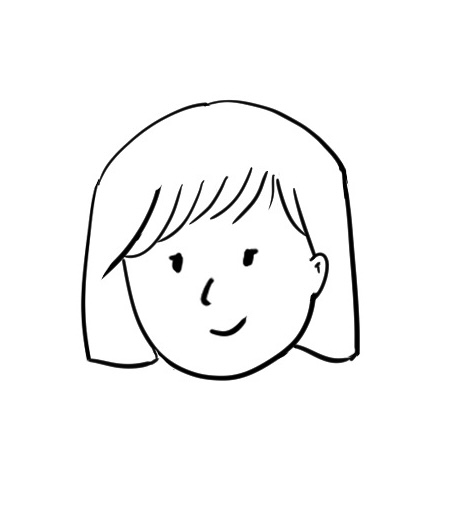
受診は無料とはいえ、せっかく高い保険料を払っているのだから適切な医療を適切なタイミングで受けたいですよね…!
私も今までは無知でしたが、今回の一件でイギリスの医療制度やサービスについて調べるきっかけになりました。
この記事で少しでも「もしもの備え」について皆さんの理解が深まったら嬉しいです!
✅ 緊急ではない体調不良 → GPへ
✅ GPが開いていない/連絡が取れない → 111へ連絡して指示を仰ぐ
✅ A&Eへ行くほど緊急ではないが、処置が必要 → UTCへ直接行く
✅ 緊急で医療が必要 → A&Eへ直接行く/ 999へ電話して救急車を呼ぶ